だって、そんなことは月も太陽も望んでいないはずだ。それなのにどこか別のところでは、それを知りたくて堪らない自分がいて、大河を駆り立てる。
竜児はおそるおそる、振り返ろうとした。たぶん「いつもならどつかれるところなのにどうしたんだろう」とかえって不安で、大河が一糸まとわぬ姿であることを忘れているのだろう。
「くぉら! 普通に見ようとすんじゃない!」
犬の頭をぽんぽん撫でるくらいの気持ちで、背中に一発見舞ってやる。幾度となくくれてやった本気の一撃に比べれば、それこそ撫でているようなもの。せいぜい竜児の意外に広い背中がもみじ饅頭になるくらい。
「おう!? あ、悪い、黙ってるもんで不安になってきて……裸だったなお前……そういや」
「油断も隙もありゃしないわねこの発情犬は……」
「それで?」
「は?」
「人に感想聞いといて『はいそうですか』もねえのかよ?」
そうだ。何も真剣に答えることはないのだ。今はただびっくりして、考え込んでしまっただけ。真正直に心の中をさらけ出すことなんてない。いつもみたいに、ちょっとした気まぐれで駄犬をからかってやっただけだ。竜児だって、その方が納得するだろう。
「あんたが日ごろ私をどんな目で見てるのかよく分かったわ。これからは変な気起こされないようにちょっとは気をつけ……なくてもいいか。あんたにそんな度胸ないもんね」
「お前自分から飛び出しておいてそれか……あのなあ、度胸とかそういう問題じゃねえ。俺はお前が……」
言いさして、やめる。私が、なに? 竜児の背中はそれ以上何も答えてくれない。何か失言したとでも言うように唇を噛んだ竜児の顔が目に浮かぶようだった。
「何よ、あんたこそ、言いかけで。最後まで言い……ぶしゅん!」
「うおっ冷て! お前人の背中に……だああっ! もう! 風呂! 行け!」
竜児はTシャツを振り払うと、大胆にも振り返った。その目は力いっぱい閉じられており、竜児の顔は赤鬼みたいに真赤だった。ずいっと手を突き出して大河の頭を見つけると、ターンテーブルよろしく後ろを向かせる。
「リモコンは探しとくから、さっさと行け!」
「分かったってば……あ、竜児」
「今度は何だよ!」
目を閉じた竜児にそっと近づいて、囁く。
「トイレ使うくらいなら、別にいいわよ?」
「……トイレ? ……んなっ!? バカ!」
下世話を咎めようにも目を開けられない竜児の手をかいくぐり、大河は浴室へ駆け出した。これで取り敢えず、竜児ははなからからかわれたと思うはずだ。最初のは遺憾な事故だったけど、相手は竜児だから別に恥ずかしくなんかない。だから照れる竜児をからかってやっただけ。竜児が真面目に返すから調子が狂ってしまったのだ。
ただ、それだけだ。
大河は浴室に入ってすぐ、何となくそこがさっき入ったときより綺麗になっているように思った。竜児が掃除したのだから元々綺麗だったのには違いないのだが、おそらくナメクジを片づけたとき、ついでに掃除をやり直したのだろう。鏡には水滴の跡すら残っていない。
そんなにピカピカにしなくていいのに。鏡はあんまり好きじゃないんだから。隠しようもない全身を映す風呂の鏡は特に。現実を見せつけられる気がするので、いつもなるべく見ないようにしている。そうでなくても毎日見下ろしている自分の身体を、何だって真正面から直視しなければならないのか。
しかし今、大河はシャワーを浴びる前に、自分の全身を映したそれと正面から向き合った。幾らまじまじと見ても、どんなに角度を変えても、やはり起伏に乏しい貧相な身体にしか見えず、分かっていたとはいえ落胆を隠せない。それでも竜児はこの身体を、綺麗だと、全然貧相じゃないと言ってくれたのだ。またいつかみたいに嘘をついて励ましてくれたのでは、とそんな思いが脳裏をかすめるが、お世辞だってやっぱり嬉しい。大河はやっと素直にそれを認めた。そんな、特別に意識しなくたって、誰にだって褒められれば嬉しいに決まっている。身体の特徴なんて中々面と向かっては言えないことを、偶然、事故で見てしまった竜児が正直なところを口にしたのに過ぎないのだ。嬉しいけど、きっとそれだけなのだろう。
でも、
「でもやっぱり、嬉しい、かも」
またぞろ口元が緩みだすのを止められないのだった。
だったら、いいよね。ただ褒められて嬉しいだけなんだから、もっと期待したって変なことではないはず。もっと見てほしいと思うのは、別に悪いことではない。
*
今度は竜児が直視できない。風呂上りの大河にグラスの牛乳を渡そうとして、竜児は危うく床をワックスがけするところだった。もしくは牛乳臭い雑巾を作るところだった、とでも。
「……お前な……」
大河は牛乳をひったくると咽喉を鳴らして一気に飲み干し、ぶはーっと親父臭く息をついた。その大河の着たパジャマのボタンは、掛け違えた上に上から二つはそもそも留まってすらいない。
赤面した竜児を、大河は嗜虐的な目で睨めつけた。
「は? 人と話すときはちゃんと目を見なさいよね。それが当然の礼儀ってもんじゃない?
あ、でもあんたの目を直接見たらショックで二三日寝込んじゃうかも。やっぱ見なくていいわ」
「俺はどこのゴルゴン三姉妹だ……」
「それでリモコンは?」
「おう」
今更ながら本来の目的に立ち返る。そういえばそれがメインだったのだ。
竜児は精一杯横目で大河を睨み、お前なあ、と繰り返す。
「普通にテーブルの上に置いてあったぞ。ちょっとは自分で探せよな。そしたらこんな……あ……いや、そんなことよりお前ボタン掛け違えてるし、その、はだけすぎだ。何とかしろ」
「あら。遺憾だわね」
「遺憾、じゃ、ねえ! お前そんなカッコでまた見えちまったらどうすんだよ!」
「さあ? どうする気?」
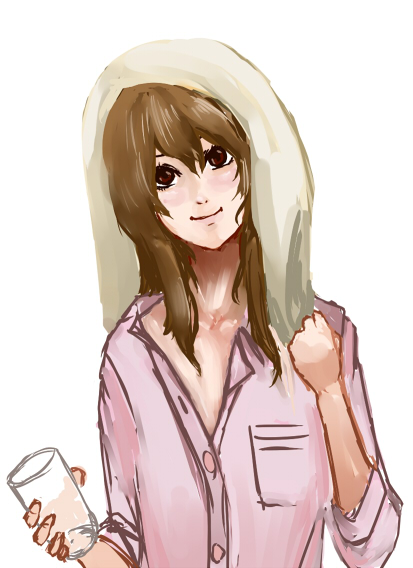
猫科の動物は食べるつもりでもない獲物を手元で生かさず殺さず、でも最終的には遊び殺してしまうという少々残酷に思える習性を持っている。やはり大河は猫科なのだと竜児は無意味に納得した。しかしそんないつもどおりの傷口をおろし金でこそげるような竜児いびりの始まりを察して、竜児は、何だ、元気になったな。よかったよかった。と、一瞬安堵する。根っからのお人好しなのである。
「……どうもしねえよ」
「ふーん、じゃあ別にいいじゃん。何が問題なのよ?」
「何ってそりゃ……お前は見られても平気なのかよ?」
「だって何もしないんでしょ?」
「しないけど、ちょっとは、恥じらいってものをだなあ……」
必死に顔を背ける竜児に、大河はじりっと近づく。その踏み出した一歩に合わせて、竜児は一歩退く。二歩、三歩と進んで下がって、アイランドキッチンに後退を阻まれる。何を考えているのか、大河はニイッと唇を吊り上げる。笑顔はただ喜びや好意を表すためのものではない。いつか何かの漫画で読んだ「笑いという行為は本来攻撃的なものであり……」云々と言う文言を、竜児は身をもって味わっていた。笑顔が怖いなんて言われ慣れているが、なまじ美人な分大河の方が、何か別の意味を含んだ笑顔はかえって怖いのだ。幽霊画が美人なのとたぶん同じ理由で。
大河は窮鼠・竜児にほとんど触れ合わんばかりに近づいた。近づいたら、もっと見えるだろう。竜児が見てくれれば、その目を透かすように大河にもそれが見えるのだ。本気にしたらいけない。だからこれは冗談だ。竜児が照れるのが面白くて、からかっているに過ぎない。それ以上の意味なんてあってはいけないのだが、もう一度、その隠れた裏側を見たくて仕方がないのだ。
「ボタン、直してよ」